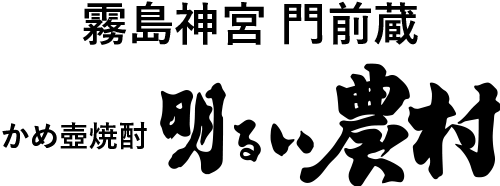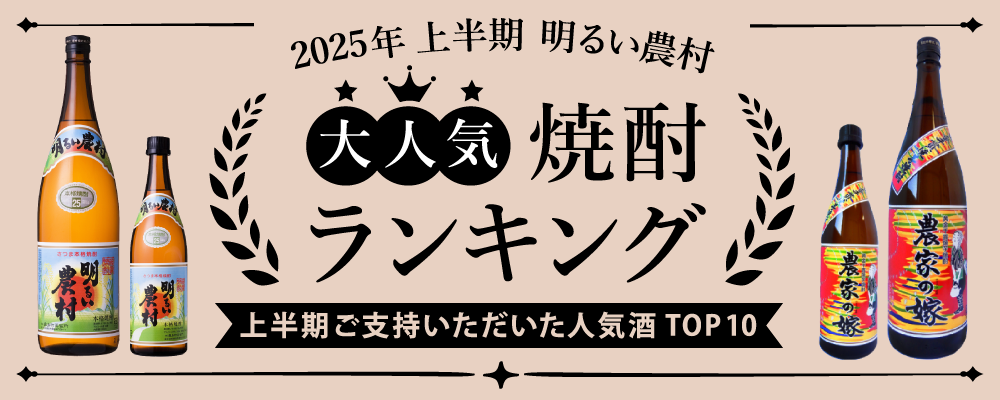芋焼酎
-
-
-
ご存じですか?「明るい農村」には、「農家の嫁」という芋焼酎もあるんです!
カテゴリー : ブログこんにちは。鹿児島の焼酎蔵「霧島町蒸留所」の阿部です。 わたしたちの代表銘柄である芋焼酎「明るい農村」は、ふく…
-
-
-
-
-
-
蔵見学時によくある質問 ~焼酎蔵「明るい農村」スタッフがお答えします~
カテゴリー : ブログよく聞かれる質問のご紹介 こんにちは(^^)/霧島町蒸留所の阿部です。 普段、お客様を蔵見学にお連れする際、よ…
-
芋焼酎、麦焼酎のおすすめの飲み方、割合について 鹿児島の焼酎蔵スタッフが紹介します
カテゴリー : ブログこんにちは(^^)/霧島町蒸留所の阿部です。 お客様とお話をする際に「芋焼酎の飲み方で一番おすすめは何?」「芋…